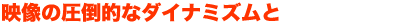

それまでの宮崎駿アニメの集大成ともいえる作品だ。まったく僕の予想をはるかに上回る出来栄えだった。とにかく圧倒的なイマジネーションの世界である。娯楽的な観点で見れば「ナウシカ」「ラピュタ」に及ばないが、そのイマジネーションの豊かさでは宮崎アニメの中でも群を抜いた面白さで、次から次へと飛び出す奇想天外な映像には始終興奮しきりである。
ハウルの城は、外観ばかりが強調されがちだが、2Dならではの表現力を見せつける内装の方がイマジネーションを刺激される。部屋の内装がアッと言う間に変わるシーンなど、その色彩と造形美、二次元アニメならではの映像のダイナミズムには驚くばかりだ。映画(Motion
Picture)とは「動く映像」のことであるが、この映画を見てから、映画の最も基本的な本質である「映像が動くこと」の楽しさを、改めて教えられた思いである。「ハウルの動く城」はタイトルに「動く」とあるように、動的な楽しさを描いた映画なのである。
外の世界の映像の美しさも特筆に値する。手書きの絵ならではの温かさがある。太陽の光が反射する湖の映像や、移動中の城のテラスから見下ろした景観の臨場感ときたら、これはともすれば実写以上の感動である。ただ洗濯物を干すシーンだけでもこれほど晴れ晴れとした気持ちにさせられてしまうとは、宮崎駿はまさに映像の天才だろう。悔しいけれど、これほどのイマジネーションを映像に表現できる者は、実写映画の監督にはいまい。宮崎駿は日本の誇りだ。
キャラクターたちの動きも素晴らしい。あのカカシが無表情でぴょんぴょん跳ねる様子。火の悪魔がステーキにかぶりつく様子。老犬がいつの間にか主人公に懐いてしまう様子など、なんとも微笑ましい。主人公に呪いをかけた荒地の魔女でさえ、そのぶよぶよの贅肉が愛くるしくみえてくる。ハウルの描き方もセンセーショナルで、鳥になったりゼリー状になったり、次々とメタモルフォーゼしていき、映像が変化することの楽しさを存分に見せつけてくれる。
賛否両論だった声優たちに関しては、僕は大賛成である。木村拓哉の演技も見事に決まっていて、本人を意識させない。倍賞千恵子も良い。18歳の時の声は第一印象では似合ってないような気もしたが、よくよく思えばモテてない後向きの女の子の役だったので、そうなるとあのあまり可愛くない声も説明がつく。90歳のおばあちゃんになってからはまさにイメージぴったり。あんな姿になっても、子供に「私は怖い魔女さ」と冗談を言ったり、自分に呪いをかけた魔女に親切にしたり、ひたすら前向きに生きていこうとする姿に宮崎節が発揮されており、感動を覚えた。しかし一番の名役者は三輪明宏だった。汗だくになって階段をあがるときのおばちゃんぶりなど絶品である。
僕が感心したのは、シーンとシーンのつながりをほとんど意識させない構成である。次のシーンが唐突に出てくるわけではなく、前のシーンの何かが発端となって初めて次のシーンにつながっていくのである。かなり意表を突いているシーンが飛び出すが、きちんとそれは道理にかなっている。「風が吹けば桶屋が儲かる」ではないが、あれだけイマジネーション豊かなごちゃごちゃした映像を次へ次へと描いておきながらも、ストーリーの筋が最初から最後まで通っている巧妙な話術には脱帽である。
恋愛映画として宣伝した宮崎アニメはこれが初めてだと思うが、そこまで恋愛映画チックになりすぎてなかったので安心した。それまでの映画と違いがあるのはキス・シーンがあるかないかだけで、あとはいつもどおり実にさりげなく恋をほのめかす形で嫌味になっていない。基本はもっぱら男性的な映像のダイナミズムで見せる娯楽大作である。やはり宮崎アニメはこうでなくては。
|
