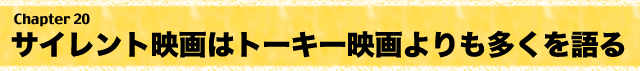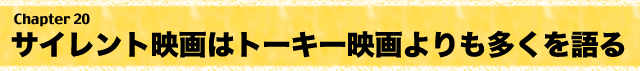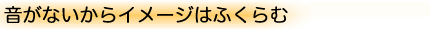
チャップリンは長年サイレントにこだわり続けた。チャップリンほどサイレントという形式に固執した者はいない。理由は「もし浮浪者が喋れば、空気が台無しになる」とのことだったのだが、『独裁者』でその気持ちを思い直したチャップリンは、早速『黄金狂時代』を改訂。浮浪者の人格を裏切る結果となってしまった。チャップリンという偉人の矛盾がここにある。ほぼ切れ目無くチャップリンの説明台詞に埋め尽くされた新版トーキー映画は、チャップリンの魔法が無惨にも消滅してしまった失敗作である。
チャップリンに限らず、サイレント映画の良いところは、「観客の想像力をかきたてること」である。サイレント映画はいってみれば詩のようなものだ。詩的情景に観客は感動するのである。チャップリンの哀愁たっぷりの演技も、サイレントだからこそ生命を宿すのである(1)。『独裁者』がトーキーでありながらもヒットしたのは、社会的なユーモアがあったからであって、『黄金狂時代』の人間臭さとは別の要素である。『黄金狂時代』の浮浪者は、独裁者ヒンケルとは違い、本来喋ってはいけないものだったのだ。
ジョージアが浮浪者を誘惑するシーン(2)は、サイレント版を見ると、ジョージアの表情と動きがこの上なく色っぽく、浮浪者の反応にも見応えがある。詩的で甘酸っぱいこの一幕が、トーキー版を見ると、「彼女は彼の髪をなでた。彼は幸せだった」という余計な解説によって、色気が半減してしまっている。浮浪者の反応もセリフに殺されて一辺倒に見える。サイレント版では、観客がジョージアの声をイメージするため、観客は、心の中で、最高に魅力的な美声を作り上げるわけだが、トーキー版ではそのイメージは一瞬にしてかき消されてしまうのだ。
情報の量は、セリフ自体はトーキー版の方が多いが、結果的には、映像に集中できるサイレント版の方が、より多くの情報を含んでいるのである。トーキー版は作品の方が一方的に観客にセリフを押しつける「受動」であるのに対し、サイレント版は、観客が一歩前に出て登場人物の感情をつかもうとする「能動」なのである。
サイレント版とトーキー版で、もっとも分かりやすい相違点は、銃声である。銃声とは、無声映画にはまったく不必要なものだ。銃は発砲すると銃口から煙が噴き出すため、映像さえ見ていれば発砲したことは容易に理解できるからだ。観客は煙を見た瞬間、心の中でリアルな銃声をつくりあげることだろう。本作のトーキー版には、銃声の効果音が入っている(3)。それまでのシーンでは、観客自身が劇中の音を補完していたのに、そこに突如と銃声音を聞けば、その瞬間、観客は夢から覚めてしまうのである。音を自分で想像するのと、用意された音を聞くのとでは、あなたはどちらが面白いと思うだろうか。おそらく自分で想像する方だろう。人の想像力に限界はないが、効果音の表現には限界がある。突如発されるこの銃声が、観客の想像を裏切った場合、それがひどく安っぽく聞こえてしまっても無理はない。
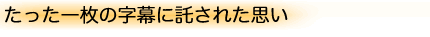
私がサイレント版で、一番感銘を受けたシーンは、酒場で大男と浮浪者が再会を果たすシーンだ。大男が「山小屋!」と叫ぶ様が、大きな字幕で表現されており、非常におかしい。その字幕に続く字幕が、浮浪者のセリフで、「ジョージア!」である(4)。大男のばかでかい大声にも匹敵する声を、同じ大きさの文字で表し、愛するジョージアへの思いをこの一枚の字幕に託している。これは『街の灯』の「あなたでしたの」という有名な字幕の原点ともいってよく、劇中最高にロマンチックである。トーキー版ではこの感動的なワンシーンが、いたって平凡なシーンになっていたのが残念である。
ここではサイレント版ばかりを褒めたが、トーキー版の褒めるべき点も多い。チャップリン自身の楽曲が堪能できるのも売りだが、山小屋が傾くシーンでの「ギシギシ」というコミカルな効果音も、サイレント版にはないおかしさとサスペンスを醸し出しており、よくできている。チャップリン自身はトーキー版の方を気に入っていたに違いないが、結局のところ、こればかりは観客の好み次第というしかない。
トーキーは奥が深い。チャップリンは『殺人狂時代』では、映像と音が互いに補完しあう演出など、トーキーでしか描けない技巧映画を作っており、私はこれでトーキーにはトーキーなりの演出の妙があることを教えられた。そしてこの演出技法が今日の映画を支えている。今後こちらでも、この問題は積極的に取り上げていきたい。
|
 |

(1)チャップリンの哀愁をおびた表情は、音がないからこそ意味がある。人間は、耳よりも、目から入る情報の方が大きい。

(2)サイレント映画では女優の発する言葉は、もっぱら観客の想像に委ねられる。ジョージアのこの色っぽい物腰に、音声など必要だろうか?

(3)銃が発砲されたことくらい、画をみれば一目瞭然だ。銃声音を入れたところで、かえって観客の想像力をかきけしてしまうのが落ちである。

(4)声ではなく、文字だからこそ得られる感動がある。サイレント映画はとかく詩的なのだ。
|