−−以前ドキュメンタリーを作られていましたが、
ドキュメンタリー製作時代に何を学びましたか?
緒方『もともと映画が好きで、映画監督になりたくて、この業界に入ったんですけど、助監督をやりながら、色んな脚本を書いたりしてたんですけども、30代のときに、ドキュメンタリーをやったときに、自分が見え始めましたね。別にそれは自己表現ということではなくて、色んな人物とか、色んな事件に出会ったときに、描くテーマみたいなものの糸口が見えてきたというか、自分がどう思うのか、ということを学んだ気がするんですね。ドキュメンタリーって結局、社会に出かけていって、色んな人に出会うことじゃないですか。そのことによって、自分の世界観であったり、歴史観であったり、自分そのものが見えてくるのがとても勉強になりましたね。30代を主にドキュメンタリーに費やしたので、やっぱりもう一度映画を作ろうと思ったきっかけにもなりましたね』
−−その経験は作品にも生かされていますか?
緒方『思いきり生かされてますね。例えばドキュメンタリーで編集するということは、何回も何回もカメラに撮られている被写体を見るわけですね。そうすると、この質問でこの人ちょっと機嫌が悪くなったな、という目線の動かし方とか行動が全部わかるようになるんです。それは演出のときに物凄く勉強になりました』
−−お互いに顔を合わせない中年男女二人の心理描写がすごくリアルだったのですが、これは監督の恋愛経験も生かされているのでしょうか?
緒方『そういうのもあるのかもしれません。一人の映画監督が、作品を作るときは、過去そのものが全部生かされているものだと思います。まさしくこの映画のテーマというのは「人は過去にふりまわされて生きていくものではないか」ということですが、実際自分が考えたとき、やっぱりその通りですよね。それは自分が昔15歳だったときの感情もありますし、あるいは僕は映画ファンですから、沢山映画を見てきたときの記憶ですとか、それらが全部集積されて、今現在2005年に作った映画の演出にはなっています』
−−製作が始まった段階からメインキャストのイメージはあったのですか?
緒方『僕が決めるんじゃないんで、それはないですよ。主役は田中さんの方からやりたいと言ってきたんです。製作の割と早い時期に、プロデューサーが「こんな企画が進もうとしているんだけど、どう思う」と田中さんに見せたらしいのですが、田中さんが乗ってきて、「あ、田中裕子。いいじゃない」と思いまして』
−−田中裕子さんは主役にピッタリですよね。
緒方『ピッタリという感覚はないんですよ。僕はいつも、俳優と文字上の登場人物が合体したときに何がみえてくるのかがテーマなんですね。田中裕子がやるんだったら、こういうことだろうなと、そこからもちろんちょっとイメージを書き直すわけです。岸部一徳さんにしろ仁科亜希子さんにしろ、タレント名鑑を見て、それこそみんなで意見を出し合って、どうかなということでやってますが、実際お会いしてみて、向こうも乗り気じゃないと駄目ですから。要は脚本の解釈というか、この人はお互い同じ方向を向けるなという印象が大事になってきます。だいたいその方が結果がいいんですよね。逆にこっちから、絶対この人じゃなきゃイヤだというのは失敗しますよね』
−−田中さんを演出していて、凄いなあと思うところは?
緒方『沢山あります。田中さんは恐るべき女優で、ミリ単位のことをよくわかっていますね。目線の動かし方ひとつだとか、あるいはリアクションの置き方だとか、すごくクレバー(手際が良い)なんですよね。最初の2・3日は色々意見のすりあわせみたいなことをやりましたけれども、4日目からはほとんど会話してないですね。向こうがこっちを信頼してるから、お互いがずれないんですよ。その意味ではすごく幸福で、スリリングな現場ではありました』
−−現場で仕事をしていて大変だったことは?
緒方『大変なことは朝が早いということ。たぶん日本映画では、これだけ朝のシーンが多い映画はないですよね。撮影35日間のうち22日間が朝3時出発でした。朝の光というのは10分で変わりますが、だんだん明けていくという本当の時間で撮影してますから、1日にワンカットしか撮れない。あれは22日間かかりました。階段を今日は下から撮って、今度は向かいのビルから撮って。しんどかったですね。撮影は夕方の5時か6時に終わって、起きるのは午前1時か2時ごろですから、お酒は飲めなかったですね。僕ももちろん大変でしたけど、スタッフも大変でした。
あと、もうひとつ大変だったのが坂道ですね。車が行けないんですよ。機材を手持ちでもっていかないといけないんで、スタッフにはちょっと恨まれましたね』
−−長崎をロケしたことで得したことはありますか?
緒方『長崎は、9歳から15歳まで住んでましたんで、今回は僕の同級生が応援する会みたいなのを作ってくれたんですが、それこそロケ場所の情報とか、現地スタッフみたいな形で動いてくれたんで、そのネットワークは助かりましたね。地元だったこともあるんで、県の方、市の方にも色々と田中さん二人で挨拶にいって、いろいろ便宜をはかってもらえましたんで、消防車もタダで貸してもらえましたし、撮影はしやすかったです』
−−長崎の坂道や市電が印象的でしたが、長崎の町並みはストーリー上、どのような効果があったと思いますか?
緒方『やっぱり階段と家々ですよね。これはどこか観念的というか文学的な話ではあるんで、その中で、大場美奈子(田中裕子が演じる主人公)という人物を肉体化させないといけないわけですが、彼女の吐息であったり、牛乳瓶の音であったりを聞かすためには坂道は必要でしたよ。これは町の話でもありますから、家々が連なったすり鉢状の町の中を田中裕子や上田耕一さんが駆け抜けていくというような、誰かに常に見られているような感覚を出したかったですね』
−−とてもリアルな作品だと思うのですが、ところどころにファンタジックな要素も盛り込まれていましたね。
緒方『話そのものを取り出した場合、実はやっぱりファンタジーですよ。30年間想い続けてきて、かみさんが死んで、付き合ってくれといわれて、やっぱり有り得ない話ですよ。基本的にリアリズムの手法で演出してますけども、ところどころに一種の寓話性みたいなものを残しておきたいなというのが狙いとしてあります。
80歳の老人あるいは、5歳の少年たちが抱えている問題を、現実として見詰めるわけにはいかないという気がしてるんですね。だからある分はリアルなんですけれども、どこかですっと昇華されるものを入れたいです。それが映画というメディアの特性だと思うんです。すべての映画って、どこかはファンタジックな部分がないと駄目なんじゃないかと思います。どんなリアリズムの重い話であろうが、何かちょっと開放されるところがないと辛いんじゃないかと。それこそ上田耕一さんの痴呆の部分は強調してますよね。それがたぶん僕の作風なんです』
−−前作「独立少年合唱団」もそんな感じがしましたが。
緒方『そうですね。僕はそんなに意識してやってるつもりはないんですけどね』
−−監督ご自身では1作目と2作目は似ていると思いますか?
緒方『それは見た人に決めてもらうのが楽しいですよね。同じ人間が作ってますから、深読みすればいくらでも似ている部分はあるでしょうし』
−−では、1作目と2作目で、違っているところは?
緒方『やっぱり俳優ですよね。「独立少年合唱団」というのは少年ばっかりで、いわゆる半分素人みたいな奴らばっかりでしたから。彼らを調教みたいな形で合宿生活という特殊な状況の中で、かなり厳しく1から演技をつけていきましたからね、まあ合宿も含めて演出だったんですけれども。「いつか読書する日」は、一癖も二癖もあるツワモノの俳優たちと自分がどうコラボレート(共作)できるかということがテーマだったんで、そこから見え方が違ってくるはずです。今でこそ伊藤敦史は顔と名前が一致しますけれども、やっぱりある程度名前を持った人がでてくると、映画の見え方が変わりますね。そのときに田中裕子、岸部一徳、仁科亜希子が見えすぎちゃうと映画としてはまずいわけですよ。物語の中で光らないといけないわけだから。といっても「田中裕子」を全部消してもダメだと思うんですよ。そこら辺はすごく悩みながら、田中さんと話し合いながら作っていきました』
−−映画が小説や絵画などの他の芸術とは違うところは何だと思いますか?
緒方『僕は「集団」だと思います。映画というのは自己表現の手段じゃないと思うんですよ。若い人の映画がつまんなくなるのはそれですよ。全部「俺が俺が」なんです。映画というのは一人じゃ作れないから、集団のエネルギーがぶつかったときに何が見えてくるかだと思います。ですから僕は脚本を書かないし、物語というのは脚本家の範ちゅうだと思っていますから、その物語を僕がどう受け止めたのか、一種の指揮者みたいな感覚ですよね。ザ・プレイヤーは田中裕子であり岸部一徳なわけじゃないですか。例えば田中裕子の役を仁科亜希子が演ったら、また全然違うものになってくる。そこが映画の面白さというかね。
だから映画の現場は一種の「磁場」だと思うんですよね。どう転がっていくかわからない面白さというのがあるんです。もしそのとき、物凄くイメージの強い監督が現れて、「こういうイメージなんだ」と全部絵コンテまで書いて、カメラまで指定したら、その映画は絶対つまらないと思う。巨匠がつまらなくなるのはそこですよね。自分で自分の世界を窮屈にしてる。その辺が僕はドキュメンタリーを作ってきたことに通じています。例えば、ドキュメンタリーも一応台本は書くんですが、台本通りにならないときの方が得てして面白いんです。僕らはこれを「うねる」というんですけど、場がうねったときの方が現場で発見があるわけじゃないですか。
「独立少年合唱団」のときに自分が課したのは「8ヶ月かけて撮ること」でした。あえて8ヶ月をかけて撮ることで、少年も成長して肉体的にも精神的にも変わるわけじゃないですか。それは一種のドキュメントですよ。ロケ現場ひとつにしたって、絵のいいところだけを選ぶんじゃなくて、あえて撮影しづらいところを選んで、そこに俳優を織り込んでみるんです。わざと苦行を自分に課すというか、そのときに何が見えてくるのか、そこに生まれてくるグルーヴ感(躍動感)、ダイナミズムみたいなものを映画に取り込んでいくわけです。
22日間夜明けをスタッフ・キャストで一緒に過ごすことになるわけじゃないですか。田中裕子と一緒に朝を迎えるということは映画にとって物凄く重要なことですよね。そうすると、余計なことがどんどんそぎ落とされていくような感覚になるんです。演出とはそういうことですよ。別に俳優に向かって「もうちょっと右向け左向け」ということではないと思うんです。その場をどう作っていくか。映画を作っていくということは、「緒方組」を作ることだと僕は理解しています。それが僕の演出です』
−−作品では何を見てもらいたいですか?
緒方『ご自分の過去をみてもらいたいですね。結局傑作というのは、人の心の中にあるような気がしますから。もちろんビジネスですから1800円の窓口もないと駄目ですが、映画ってスクリーンだけじゃなくて、人の心に入ったときに初めて完結するんですね。賞をもらうとかヒットするとかじゃないと思うんです。映画によって、あなたがどうなるんですか、どう思うんですかということを問うてるわけです。この映画だったら、過ごしてきた日々みたいなことを自分に置き換えて見て頂けるといいのかなという気がします』
−−年配の人と若い人、どちらに映画を見てもらいたいと思っていますか?
緒方『年配の人に見てもらいたいですね。やっぱり年配の人でも映画が好きな人って沢山いるわけですが、最近映画館に行ってない人があまりにも多いんで。
年をとることは、お金も入ってくるし、どんどん自由になるはずなんだけど、肉体の衰えだったりとか、地位の問題だとか、どこかで不自由になるんですよ。自由さと不自由さの両方を抱えて、その狭間でうろうろしている人たちに、これを見てもらいたいんですよね。だからそんなに派手なシーンは決してないし、船も沈まないし、宇宙で戦争も起こりませんけれども、映画はやっぱり僕は見世物ではなく、見えないものを映すものだろうと思っているんで。それは例えば人を好きになったときの気持ちであったり、心の揺れであったり、葛藤であったり、あるいは空気であったり、ようするにパッと目にわからないもの。宇宙船がドッカーンと爆発すれば目に見えるじゃないですか。そうではなくて、人の心のひだみたいなものを映すものが映画だと僕は思っていますんで、そこを見たい人は映画館に来てください』
「いつか読書する日」をAmazonで買う
|
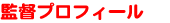
1959年佐賀県生まれ。高校時代から8ミリ映画を撮り始める。福岡大学在学中に石井聰亙と出会い、映画監督を志して上京。「狂い咲きサンダーロード」(80年)などの石井作品で助監督を務めるかたわら、自主制作映画「東京白菜関K者」(80年)を監督。この作品はぴあフィルムフェスティバルにて入選。その後、高橋判明監督や大森一樹監督らの助監督を務め、86年にフリーディレクターとして独立。CMやミュージックビデオ、ドラマなどを多数演出。90年代には「ETV特集」「驚きももの木20世紀」など、テレビドキュメンタリーを中心に活躍。作品本数は100本を超える。
00年「独立少年合唱団」でスクリーンデビュー。この作品は、第50回ベルリン国際映画祭コンペ部門で新人監督賞にあたる「アルフレートバウアー賞」を受賞。日本人初の受賞となった。
最新作「いつか読書する日」は長崎を舞台に中年男女の不器用な恋を描いた作品。

「いつか読書する日」
2005年製作
配給・宣伝:スローラーナー
監督:緒方明
出演:田中裕子、岸部一徳、仁科亜季子、渡辺美佐子、上田耕一、香川照之
プロデューサー:追分史朗、畠中基博
脚本:青木研次
音楽:池辺晋一郎
撮影:笠松則通
製作:パラダイス・カフェ、パグポイント・ジャパン
公式サイト:http://www.eiga-dokusho.com/
7月2日(土)よりユーロスペース他で公開

▲35年間、お互いに避けていながらも、心の中では忘れられず、単調な日々を生きてきた中年男女、大場美奈子(田中裕子)と高梨槐多(岸部一徳)のラブ・ストーリーです。美奈子はその思いをラジオの投書でしか打ち明けられません。槐多も美奈子の顔を見ることができません。ついに二人が出会った瞬間、積もり積もった何かが弾けます。感動的です。

▲上田耕一さん扮する痴呆のおじさんの描き方は、ある種ファンタジーとも言えます。緒方監督の特徴は、重々しくもリアリズムに徹していながら、このようなおとぎ話チックなところがあることです。

▲「いつか読書する日」には様々の人物が登場し、交錯しあう「群像劇」ともいえます。渡辺美佐子さん演じる小説家は、大場美奈子をモデルにして小説を書いており、作品の狂言回し的な存在になっています。

▲槐多は、牛乳を飲めないのに、牛乳配達に来てもらっています。それはなぜか。美奈子が牛乳配達をやっているからです。槐多の奥さんは、死を前にして、初めて夫の本心に気づきます。

▲30年前、美奈子の母と、槐多の父は、恋人関係であり、デート中に事故死したという設定になっています。いかにもメロドラマらしい悲劇的な過去が物語を盛り上げます。

▲「独立少年合唱団」で教師役を演じていた香川照之さんが今回も出演しています。今度はスーパーの店長役で、短い出番ながらもキラリと光る存在感を見せつけてくれます。
<緒方監督と会って思ったこと>
「いつか読書する日」で、中年男女の恋を描いているとあって、監督はそれなりに年とともに深まる人間味の豊かさを感じさせる方で、その経験を映画にも生かすことができる人だと思いました。どのような質問にもすぐに的確な答えを出し、そこからどんどん話題を膨らましていただいたので、インタビューが楽でした。
映画の作風は割と静かで重たい感じがしましたが、監督本人は気さくで包容力のある、面白い方でした。僕は一人で取材したので、インタビューと写真撮影を別個にしなくてはいけなかったのですが、写真撮影の際、僕が「会話しているときの自然なところを撮りたいのですが」とわがままな注文をつけると、監督はすぐに僕の前で喋っているふりをしてみせました。これが仕事とはいえ、監督にここまでしていただけると僕としても嬉しかったです。
緒方監督は映画を作る側の人であって、僕は映画を批評する側の人です。つまり監督と僕はまったく正反対の次元にいるわけですが、やはり映画に対する捉え方は、僕のような撮影現場を全く知らない素人とは全く異質であることがわかりました。特に僕は映画は自己表現そのものだと思っていたので、監督に「映画は自己表現じゃない」と言われたときにはドキッとさせられました。その意味では、僕自身もかなり学ぶことが多かった1日でした。
2005年6月24日
パラダイス・カフェにて
取材担当・澤田
|