![]()
企画5
摩訶不思議な空想映画の世界
|
|
| なぜSF映画は男心をくすぐるのか |
| さっきもいったように、僕はSF映画で育った。SFの面白さは、僕らの日常では考えられない未知の世界を体験できることにあると思う。そう、ごっこ遊びの楽しさがSF映画にはある(僕は大のごっこ好き少年だった)。「スーパーマン」を見て悪と戦うヒーローの気分を味わったり、「宇宙戦争」を見て宇宙人の襲来に恐怖を覚えたり、そういうロマンが、男心をくすぐるのであり、だからこそSF映画は面白いのだ。 セットデザインの興味も、SF映画の醍醐味で、例えばひとつの部屋を描くにしても、丸い部屋だったり、カラフルな部屋だったり、映画によって全く異なったデザインを見ることができる。 僕は「シンドバッド七回目の航海」の骸骨と決闘する場面を見たときには、真似して大暴れしたことがあるが、こういう特撮もSF映画の見所である。動くはずの無いものが動いただけで、僕らは単純に感動してしまうのである。 このようにセットや特撮など、視覚に訴えるユニークな見所が、珍しいものに興味を抱こうとする僕らを引きつけてやまない。昔はSFはB級映画であり、ヒット不可能なジャンルといわれていたが、今となっては、もっとも観客を引きつけることのできるジャンルにまで発展しているが、これも摩訶不思議な映像を見たいという我々の欲求が要因しているのかもしれない。 |
| 怪物に生命を吹き込んだ新技術 |
| SF映画・ホラー映画につきものなのが、架空のクリーチャーである。 巨大な化け物から小型のロボットまで、SF映画にはあらゆる怪物が登場し、我々を大いに楽しませてくれるが、映画を見ていて、ふと「どうやって撮影してるんだろう」と思うことがある。まるで本当に生きているかのようだが、こういう風に怪物を完成させるまでに、技術者たちは大変な努力をしていることを分かっていただきたい。  昔の映画の場合、俳優がマスクをつけて怪物を演じるのが精一杯だった。しかし、「キング・コング」で新しい技術が確立される。ストップモーション撮影を駆使した”ダイナメーション”である。これはウィリス・H・オブライエン(左写真)という人物がほぼ一人だけで磨き上げた特殊技術である。精巧に作られた人形を慎重に動かして、微妙に動きをつけて1コマずつ丹念に撮影していく。フィルムは1秒間で24コマなので、たった1分のシーンを撮影するにも相当な労力である。オブライエンはたった一人でこの作業を指揮したのだから凄い。キング・コングが人間様を虫コロのように殺す演出は、肉付きも見事で、それはもう重量感と迫力に満ちた演出であった。この技術はレイ・ハリーハウゼンに引き継がれ、長いことSFXの花形であった。 昔の映画の場合、俳優がマスクをつけて怪物を演じるのが精一杯だった。しかし、「キング・コング」で新しい技術が確立される。ストップモーション撮影を駆使した”ダイナメーション”である。これはウィリス・H・オブライエン(左写真)という人物がほぼ一人だけで磨き上げた特殊技術である。精巧に作られた人形を慎重に動かして、微妙に動きをつけて1コマずつ丹念に撮影していく。フィルムは1秒間で24コマなので、たった1分のシーンを撮影するにも相当な労力である。オブライエンはたった一人でこの作業を指揮したのだから凄い。キング・コングが人間様を虫コロのように殺す演出は、肉付きも見事で、それはもう重量感と迫力に満ちた演出であった。この技術はレイ・ハリーハウゼンに引き継がれ、長いことSFXの花形であった。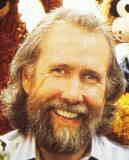 やがて、「セサミストリート」のジム・ヘンソン(右写真)によって、操り人形による特殊技術も確立される。彼の「ダーククリスタル」は、人形がまるで人間のような動作と表情を見せ、大衆をあっと驚かせた。こういう技術が、後のロボット動物”アニマトロニクス”へと進展していくことになる。 やがて、「セサミストリート」のジム・ヘンソン(右写真)によって、操り人形による特殊技術も確立される。彼の「ダーククリスタル」は、人形がまるで人間のような動作と表情を見せ、大衆をあっと驚かせた。こういう技術が、後のロボット動物”アニマトロニクス”へと進展していくことになる。ダイナメーションなどの技術は、「タイタンの戦い」、「スター・ウォーズ 帝国の逆襲」、「ロボコップ」などでも多様され、少し前のSF映画には欠かせないものであった。しかしこのダイナメーションには欠点があった。1コマ1コマがくっきりと写り過ぎるので、映像にぎこちなさが生じてしまうのである。 そこで新技術が生まれる。そう、”CG”の導入である。80年代からCGは積極的に使われていたものの、まだ重宝されてはいなかったが、「ジュラシック・パーク」の誕生により、たちまちSFX技術の中核となる。「ジュラシック・パーク」は、当初ダイナメーションで撮影されていたが、CGに変更された。CGの技術は目覚ましく、陰影も自由に付けることができ、動いたときの自然なブレもしっかりと表現可能で、とても合成とは思えない映像を作り出すことができる。まるで恐竜が本当に襲いかかってくるようで、劇場内では悲鳴が響き渡った。これは革命的であった。 以後、CGは「フォレスト・ガンプ/一期一会」、「タイタニック」など、SF以外の作品でも頻繁に利用されるようになり、映画のクオリティを格段に上げる役目を果たしている。 ただしCGにも欠点はある。CGはダイナメーションやアニマトロニクスに比べ、重量感が出しにくいのである。ここをどうカバーしていくかが、フィルムメーカーたちの今後の課題となるだろう。 |
| スターの座を勝ち得たホラー映画界の怪物たち | ||||
 |
 |
 |
 |
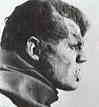 |
| ホラーという言葉は広義であり、ゴシックロマンからサスペンスからスプラッターから意味は幅広いが、一般的に言うホラーといえば、観客に恐怖感を与えるものをいう。観客も恐怖中枢が肥えてきているので、時代につれてホラーも急速に変化していったが、やはり戦前のホラーが最もシンプルで、掴みやすかったと言えよう。 戦前のホラー映画は、今見てもさほど怖くはないが、映画マニアにはたまらない楽しみがある。登場する怪物が”創造の起源”といえるほど分かりやすく、ユニークだからである。 「フランケンシュタイン」のあのごっつい怪物や、「魔人ドラキュラ」の黒いマントのドラキュラ伯爵など、公開当時は相当なインパクトであり、イメージを決定づけている。これらが公開された4・50年も後に生まれた僕らでさえ、フランケンシュタイン・ドラキュラといえば、この30年代のフランケンシュタイン・ドラキュラの顔を思い浮かべてしまうのだから、当時の衝撃がいかに強いものだったか、分かるというものだ。こういった怪物はもはや観客を引き込む大スターであった。だから、ホラー映画専属スターともいうべきロン・チャニー、ボリス・カーロフ、ヴェラ・ルゴシという名役者も誕生したのである。60年代に現れたホラー御三家ヴィンセント・プライス、ピーター・カッシング、クリストファー・リーの3人も少なからず彼らの影響下にあったといいたい。 現在も沢山のホラー映画が生み出されているが、アイデアが模倣したものばかりなので、ホラーの指標記号となれるほどの印象的なキャラクターはなかなか誕生していない。敢えていえば”残虐さ”を売りにした「13日の金曜日」のジェイソン君ぐらいだろうが、昔のホラー映画独特の美学的趣がないのは、残念な話である。 |
||||
| SFX技術革新に貢献した偉人たち | ||
| 「月世界旅行」で特撮技術の基礎を築く。 宇宙人が一瞬にして煙りになるシーンなど、有名である。 |
「メトロポリス」でSFの概念を打ち立てた巨人である。 近未来都市の映像感覚は知識人を驚かせた。 |
|
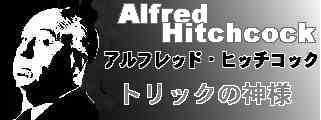 |
||
| 恐怖映画の神様といわれている名監督だが、 独創性溢れるトリック撮影の妙味も有名である。 |
「2001年」でSFのイメージを覆した鬼才である。 この他「博士の異常の愛情」など、強烈な作品が多い。 |
|
| 人形を少しずつ動かしてアニメを形作るSF技術 <ダイナメーション>を最大限に生かした偉人だ。 |
空想科学小説家としても有名なクリエーターである。 想像を絶したアイデアで多量の娯楽作を生んだ。 |
|
| 「2001年」、「スタートレック」、「未知との遭遇」、 「ブレードランナー」等を手掛けた特撮作家のナンバー1。 |
単なるSFに終わらず、独特な美学を見せて、 カルト的な人気を得ている有名監督である。 |
|
| 古典SFといえる「地球の静止する日」を監督、 他に「アンドロメダ・・・」などでSF映画の名手となる。 |
「スター・ウォーズ」を発表し、大成功を収める。 プロデュース業に熱心。CG専門の会社ILMを持つ。 |
|
| 空想映画の歩み | ||
| アインシュタイン/相対性理論 リンドバーグ/大西洋無着陸飛行 エンパイアステートビル完成 チューリング/コンピュータ論 H・G・ウェルズ死去 広島に原爆投下 IC開発 サンダーバード放送開始 アポロ11号月面着陸 ゲイツ/マイクロソフト社創設 フィリップ・K・ディック死去 ファミリーコンピュータ発売 ホーキング/ブラックホール論 手塚治虫死去 |
1902年 1905年 1924年 1927年 1931年 1933年 1936年 1939年 1945年 1946年 1951年 1953年 1954年 1956年 1958年 1959年 1966年 1968年 1969年 1971年 1972年 1973年 1974年 1975年 1977年 1978年 1979年 1982年 1983年 1984年 1985年 1986年 1988年 1989年 1990年 1992年 1995年 1996年 1998年 1999年 |
月世界旅行 バグダッドの盗賊 メトロポリス、蒸気船ウィリー フランケンシュタイン、魔人ドラキュラ キング・コング、透明人間 フラッシュゴードン、来るべき世界 オズの魔法使 美女と野獣 地球の静止する日、遊星よりの物体X 宇宙戦争 海底2万哩、ゴジラ ボディ・スナッチャー、禁断の惑星 シンドバッド七回目の航海 タイムマシン ミクロの決死圏、華氏451 2001年宇宙の旅、猿の惑星 時計じかけのオレンジ、THX-1138 惑星ソラリス エクソシスト、スリーパー 未来惑星ザルドス スター・ウォーズ、未知との遭遇 スーパーマン エイリアン、スター・トレック E.T.、ブレードランナー、トロン 銀河伝説クルール ターミネーター、ネバーエンディング・ストーリー バック・トゥ・ザ・フューチャー ザ・フライ ウィロー アビス トータル・リコール ジュラシック・パーク トイ・ストーリー インデペンデンス・デイ ディープ・インパクト、アルマゲドン マトリックス |