【な】
直し [脚]
第一稿が書き上がった後に、シナリオを書き直すこと。出来の善し悪し、製作費の問題、倫理的な面など、様々な理由でシナリオは必ず何度か書き改めることになる。
長回し [撮] 
20秒以上のカット。
ナグラ Nagra [撮]
ポータブル・テープ・レコーダーの商標名。ドキュメンタリー映画の撮影などで活躍。
70ミリ 70mm [撮]
撮影用フィルムの種類のひとつ。テレビに対抗して映像の巨大さを売り物とした。フィルム幅が70ミリワイドサイズで、両端に4つの磁気サウンドトラックが塗られており、上映しても映像の粗が気にならなかった。「アラビアのロレンス」での砂漠の広大なる映像は、まさしく70ミリ・フィルムの成せるワザだ。70ミリの映画をテレビ放送する場合、そのまま放送してしまうと、被写体が小さすぎてわかりにくくなってしまうので、画面をトリミングする必要がある。【写真は35ミリとのサイズ比較】
→35ミリ、16ミリ、8ミリ
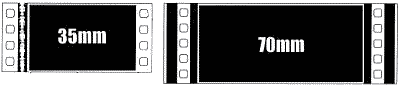
ナマ [映]
業界用語で、売上げ。
生音 foley [編]
道具などを使ってそれらしい効果音にしたもの。
生フィルム [編]
未現像のフィルム。
生放送 [他]
収録したものを放送するのではなく、スタジオもしくは現場で写しているものを直接放送すること。テレビ用語。
生もの [他]
インタビューやイベントなどを開催するとき、それに出席する役者や監督を指す俗語。
生録音 live recording [編]
聴衆の前で録音したテープ。
なめる [撮]
画面内に手前の被写体の一部を入れて撮影すること。
→肩なめショット
奈落 [他]
演劇用語で、舞台の下のこと。
ナラタージュ narratage [編]
ナラティブ(解説)とモンタージュ(組立)の合成語で、過去の事件を描いた回想シーンなどをナレーションで説明していく表現形式。
ナレーション narration [脚]
画面外からの声。シナリオではセリフの前に「N」と書いて示す。画面を解説したものだけでなく、心の声、回想シーンの外の会話などもナレーションという。テレビでは、小さい画面を見ただけではわかりづらいところもあるので、ナレーションはよく使われる。劇場用映画をテレビ放送するとき、ナレーションが新たに加えられることもある。
ナレーター narrater [演]
ナレーションを読む人。語り手。とくにテレビ番組やドキュメンタリー映画で活躍することが多いが、「バリー・リンドン」のマイケル・ホーダン、「愛人/ラマン」のジャンヌ・モローのように、劇映画でも重要な役割を果たすことがある。