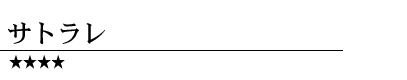|
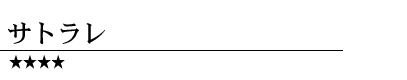
■訴求力のあるこの企画をどう膨らますか
やたら高尚な作品をつくろうとする傾向があるこの映画業界で、ボツになってもおかしくない大恥ずかしの企画を本気で映画化してしまった。まったくよく作ったものだと感心してしまう。いっけんテレビドラマのような安っぽさがあるが、しかしこれがおもしろすぎるのだ。
もともと原作の漫画がよくできていた。心の中で思ってることがまわりの人たちに聞こえてしまう症状を持つ人と、その人を取り巻く周囲の人たちがどんな生活をしていくのか、という発案はなかなかおもしろく、それだけでもかなりの訴求力がある。あとはその案をどれだけふくらませられるかというのが課題だが、やはり案そのものが強すぎるせいで、観客もある程度はストーリーを予測しがちである。だから予想通りの展開になると、最初のうちは幾分か興が冷めてしまうのだが、これがしだいに話の流れに、すなおに乗せられてしまうのである。これは後半に秘密が隠されているからである。
■観客の幼心を想起させることが秘訣
ふつうのドラマでは、話のシチュエーションと、役者の表情、カメラの構図、音楽の雰囲気などが、その場その場の登場人物の感情を表現する。
そこで本作について考えてみよう。本作では主人公だけ何を考えているのかセリフではっきりと説明させている。なので、観客の意識は最初はどちらかといえば周囲の人間の方に置かれてしまうだろう。主人公を第三者の目から観察するのである。それが前半部の特徴である。
ところが後半部からはちがう。観客の意識がしだいに観客自身へと向けられるのである。それがこの映画の傑作たる秘密である。主人公の心の声は、しだいに観客に「自分ならここでどう思うだろう」と考えさせる。やがては観客の幼心までも刺激し、観客の過去の思い出を想起させるのだ。それは母に可愛がられた思い出である。僕はこの映画のテーマは親子愛ではないかと考えている。子は親には何も言わないものだが、心の中ではほんとうに感謝しているものだ。その無意識の気持ちを、あえて言葉にして何度も何度も連呼しているがゆえに、心の底から感動がこみ上げてくるのである。
母と子でなく、おばあちゃんと孫という設定にしたことも成功の秘訣である。日本人は母と子の関係ではあまりピンとこないだろうが、おばあちゃんと孫というのはわかりやすい。孫はおばあんちゃんに甘えるものだからだ。そのことが、結局は観客の母の思い出を想起させる。本作は母と子のノスタルジアなのである。
|