|
|
■ミュージカルはミュージカルでなければならない ミュージカルは68年の「オリバー!」を最後にして、ほぼ映画界から消えたといってもいい。完全に消えたというわけではないが、たまに作られるミュージカルは本当にミュージカルと言えるものではなかった。本当のミュージカルというものは、色鮮やかで、情熱的で、きらびやかでなければならないのである。街のみんながいっせいに踊ったり、空に花火があがったり、それがミュージカルなのである。「ムーラン・ルージュ」はそのすべての要素を備えている。 本作は実に映画ファンにとってはありがたい一本である。まず目を奪われるのがその色彩感覚である。カラフルで美しく、それはひと昔前の総天然色映画を思わせる懐かしさがある。赤青黄の原色のダンサーたちがカンカンを踊っているのを見たときにはつい嬉しくなる。 オリバー・ツイストの物語を華麗なミュージカルにアレンジしたとき、そのタイトルを「Oliver!」と銘打ったように、ムーラン・ルージュの物語を華麗なミュージカルにアレンジした本作は「Moulin Rouge!」と銘打ち、往年のミュージカルをマルチメディア時代の解釈で大げさなまでに、ここに復元させた。まさに「!」な作品なのである。しかし日本では情けなや、感嘆符を取り除いて単に「ムーラン・ルージュ」としてしまった。原題の感嘆符がどれだけ重要なのかを何もわかっていないのである(もっとも、ムーラン・ルージュという言葉自体に華やかさがあるにはあるが)。 「ミュージカル」という言葉で言えば、申し分ないが、それだけでしかないのが惜しい。たいして重要でないカットにも不必要に特殊効果をかぶせたことが、せっかく作り込んだ幻想世界の魔力を弱くしているのも気になる。しかしヒット曲をふんだんに使って、ミュージカルを何も知らない観客たちに、モノホンのミュージカルの劇的魅力を教えこませた手柄は褒めたい。バズ・ラーマンの野心は、しかと受け止めさせてもらった。将来彼が大監督になったとき、きっと本作も再評価されることを予知しておく。 |

|
| http://cinema-magazine.com |

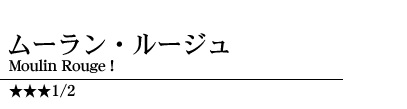
 名作一本 No.70
名作一本 No.70