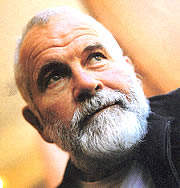|
|
■前代未聞の興行戦略 「ロード・オブ・ザ・リング」は3部作で1本の映画として成り立つ。3本の映画をまとめて撮ったというよりは、1本の映画を3回に分けて公開しようというのである。前代未聞の興行戦略である。 1作目は2作目を期待させる形で、いったん幕をおろす。このエンディングの見せ方は、見た目以上に斬新である。次回作を期待させて終わるというパターンは、過去の映画にも少なからずあったが(テレビの帯ドラマなどは毎回のようにやっていることだ)、「ロード・オブ・ザ・リング」の1作目のラストがそれら一連のシリアルものよりも優れているのは、次回作を期待させながらも、ひとつの大きなテーマが完結しているからである。かつてなかった感動と期待がそこにあって、2作目を1年先までじらす戦略が、さらにこのラストシーンを感慨深いものにしている。 あきらかに商業精神丸出しであるが、映画の表現法としても興味深く、作家主義と商業主義の二要素が相乗効果をあげた極めて稀なケースだと断言する。ただしこの効力が持続するのは来年までだというのも付け加えなければならない。1作目はまだ序幕であり、2作目3作目の出来次第によっては大きく価値が変わると考えられる。よって、現段階では1作目の評価はしづらい。正直、私は3部作すべてを見るまでこのコーナーで取り上げたくはなかったのだが、よくよく思えば、1作目の商業価値を決めるのは今しかないことに気づく。
■ファンタジーとは? タイトルをあげるまでもなく、だいたい今までに作られてきた中世の幻想世界を描いた映画のほとんどは失敗に終わっている。理由として一番考えられるのは、期待への裏切りだ。「ファンタジーはそんなのじゃない」「ムードのぶちこわし」という罵声が飛んでくる。 (ゲームを例に取るのはしゃくかもしれないが)映画とゲームとではやはり見せ方はまるで違うのであって、オタクたちがゲームどおりの内容を期待しても始まらないことである。ゲームでは色々なモンスターを相手に死闘を繰り広げて楽しいが、ただ座って見ているしかない映画では、最初から最後まで死闘の映像では途中で飽きてしまう。映画ではモンスターの数をしぼり、登場人物を膨らませながらも、ひとつのエピソードを拡大させて描くことが大切である。しぼられたエピソードがオタク心に届いてくれればいいのだが、さすが「ロード・オブ・ザ・リング」は自称ファンタジーオタクであるピーター・ジャクソンの手にかかったので、みごとにジンクスを拭い落として、初めて認められたファンタジー映画となった。「剣と魔法の物語はこうあって欲しいものだ」という願望が形になった本作は、エピソードのひとつひとつが期待以上のものである。本作は「ファンタジー」であることが最大の見せ場なのである。ジャンルそのものが技術的なものよりも注目されたのはかれこれ30年ぶりの珍事。本作はきっと映画史の1ページに記録されることであろう。ファンタジーの歴史は、小説も映画も「ロード・オブ・ザ・リング(指輪物語)」から始まるのである。
■映画には映画なりの力がある それにしても、あの小説をよくしぼってくれたものだ。しぼってしぼって、ひとつのエピソードを膨らまして見せるのは良いことだが、たまに膨らましすぎて、登場人物の行動や言動が臭くなってしまったところも何点かあり、幾分か不満が残った。 |

|
|
|
||||||||||||||||||||
| http://cinema-magazine.com |