| 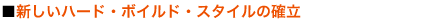
職業監督の時代が古いものとなり、自主制作からプロになる時代の訪れを告げた60年代。多くの監督が生まれたが、中でも最も活発で、異彩を放っていたのがマーティン・スコセッシ(1942-)である。学生時代から映画にのめりこみ、独自に映画を研究しつつ、金を盗んでまでして自主制作に打ち込んでいた青年スコセッシは、カサベテスの「フェイシズ」を見てますます感化され、そこに映画製作のノウハウを見いだす。まもなく「ドアをノックするのは誰?」を発表。一緒に映画界に招いた主演のハーベイ・カイテルはそのときからスコセッシ映画の常連となり、以降スコセッシは同じ仲間同士で映画を撮るファミリー的なやり方に落ち着く。
スコセッシ映画は、そのムードから「色彩のフィルムノワール」と表現してもいいものだった。50年代に流行ったフィルムノワールの要素を取り入れ、それを70年代のニューヨークなりのコアな表現に脚色し、屈折した新しいハードボイルド・スタイルを確立。色にこだわったそのカメラワークは、何でもない小道具を写しただけの映像にもムードがあった。
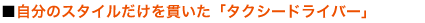
「タクシードライバー」はスコセッシが自分自身のスタイルだけを貫きとおした、ある意味、実験映画である。主人公の主観的映像だけで描ききった「自分スタイルのためのスタイル映画」であり、ワンカットワンカットがスコセッシそのものである。主演のデ・ニーロには首は動かさず、目の動きと表情だけでストーリーを物語るように指示。カッティングの表現も手伝い、映像のひとつひとつに登場人物の息づかいを感じさせる。スコセッシの映像は、暗く、静かなものにも、このような「生きた空気感」があり、これがスコセッシ映画を支える最も重要な要素になっている。第二の実験映画「レイジング・ブル」を含め、スコセッシ映画のほとんどにこの「生きた空気感」は活かされている。
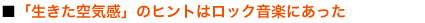
「生きた空気感」のヒントはロック音楽である。スコセッシは、映画を物語としてではなく、ロック音楽のように、人のセンスに訴えるものとして捉えていた。直接ロックを描く「ラスト・ワルツ」は、コンサートの映像でありながらも、そこにはまったく観客を意識させない。カメラは演奏者の表情だけを接写しており、映像からは熱気があふれでんばかりである。この空気こそ、スコセッシ映画の根底になっているものである。ロック的カラーに彩られた「最後の誘惑」は、ストーリーよりも、映像を重視して、映像のセンスだけで登場人物の心理を描写しており、我々見る者を本能的に刺激する。これは極めて稀なことであり、スコセッシだけが持つ他に類を見ない才能なのである。
|